「◯◯さん、普通退職かぁ。優秀だったもんな…」
公務員として働いていると、よくそんな場面がありますよね。
迷いつつも公務員を辞めたい気持ちを抱えていると、辞めていく先輩や同僚の決断をみて、なんだか少し取り残されたような、羨ましいような気持ちになりませんか?
安定していると言われる公務員の世界。でもその内側には、優秀な人ほど辞めざるを得なくなる“構造的な理由”が潜んでいます。
一方で、同じ環境で働き続ける人たちもまた、違った意味で優秀さを発揮しているのです。
この記事では、実際のエピソードを交えながら
- 優秀な人が公務員を辞める背景
- 優秀な人ほど公務員を辞める理由5選
- 公務員を続ける人も優秀な理由5選
を解説します。
「辞めるのも続けるのも、どちらも優秀」
そのうえで、自分はどんな優秀さを選びたいか。
 はなこ
はなここの記事を読みながら、一緒に考えてみませんか?
優秀な人が公務員を辞める背景


一見、公務員は安定していて恵まれた職業。
でもその内側には、優秀な人を“外に押し出してしまう構造”が存在します。ここではその背景を俯瞰して整理します。
1.人事評価の仕組み
公務員の評価は年功序列が基本。成果を出しても昇進や給与に直結しにくく、成長意欲が高い人ほど「ここにいたら機会損失では?」と感じやすいのです。
2.ゼネラリスト型の人材育成
数年ごとの異動が前提で、せっかく積み上げた専門性やネットワークもリセットされがち。キャリアの軸を築きたい人にとっては大きなハードルです。
3.属人化する業務
複雑な仕事ほどマニュアル化や仕組み化されておらず、能力のある人に仕事が集中します。優秀な人ほど便利屋になり、疲弊してしまうのです。
4.意思決定のスピードと裁量の小ささ
前例踏襲の文化、決裁の煩雑さにより、仕事のスピードはどうしても遅くなります。もっと自由に挑戦したい人にとっては大きな制約です。
5.外部の労働市場の変化
リモートワーク、副業、専門職としてのキャリア…。公務員の外にも多様な選択肢が広がっています。「もっと自分らしく働けるかも」と思えば、外に出る判断は自然なことです。
こうした構造的な背景を考えると、優秀な人が辞めるのは必然とも言えるのです。



実際、私の周りでも「個人の努力ではどうにもならない」と気づいて辞めていった優秀な先輩が複数いました。
優秀な人ほど公務員を辞める理由5選


では、優秀な人はなぜ公務員を辞めていくのでしょうか?理由を5つ解説します。
1.専門性や情熱を活かせない「異動ガチャ」
公務員のキャリアはローテーション人事が前提。数年ごとに部署が変わり、これまで積み上げた経験やネットワークがリセットされてしまいます。
実際、私の先輩で子育て支援に強い情熱を持っていた先輩Aがいました。
「住民のためにできる支援は何か」と心から考え、仕事に誇りを持っている人でした。
ところが、その優秀さゆえに本人の希望とは関係なく、他部署からの引き抜きがありました。
「このままでは自分の軸を失ってしまう」と感じた先輩Aは、退職を決断。
その後の行動もとても印象的でした。
- 退職前に有給休暇を使って海外の子育て支援の現場を学びに行く
- 帰国後に正式に退職
- 民間の子育て支援企業に転職
自分のやりがいや誇り、専門性を守るために、外に出るという選択をしたのです。
2.できる人に仕事が集中する構造
仕組みより「人」に依存する文化のため、能力のある人ほど業務が集中します。
政策企画課で長年働いていた先輩Bは、上司からも厚い信頼を受け、新しい部署の立ち上げメンバーに選ばれるほど。
ところが、部署が軌道に乗ったところで退職しました。
理由は「できる人に仕事が集まりすぎて、常に激務になる」構造に限界を感じたからです。
3.表面的なことばかりで、構造や仕組みを改善できない
そもそも公務員の世界では、法律や制度、組織文化に縛られて根本的な改革が難しい現実があります。
たとえ現場から「もっと仕組みを変えよう」という声が上がっても、決裁や前例の壁に阻まれてしまう。
その結果、優秀な人ほど「結局、この組織では本質的に変えられない」と感じ、外に出る選択をするのです。
辞めると申告した先輩Bに対して、上司からは「正規職員ではなく、非常勤で出勤日数を減らすという選択肢もある」という提案。
でもそれは、本人の悩みの本質には全く触れていない“表面的な改善策”。
先輩は「給料だけが下がって業務量は減らないのが目に見えている」と怒りをあらわにしていました。
問題は「仕事量の調整」ではなく、「できる人に業務が集中する仕組み」そのものだったからです。
4.スピード感の限界
どんなに優秀でも、役所の仕事は多重決裁や調整に時間がかかります。
一つの企画を動かすだけでも、議会を通した予算取りや何人ものハンコをもらわなければならない。
「もっと早く動ければ助かる人がいるのに」と思うほど、スピード感のある現場に飛び込みたくなるものです。



特に挑戦意欲の高い人ほど、このギャップに耐えきれず退職を選びます。
5.自分の人生を主体的に選びたい
優秀な人は「環境に流されるのではなく、自分で選びたい」という意思を強く持っています。
子育て支援の先輩Aが海外研修に飛び出したのも、自分の軸を守るための行動でした。



異動や制度に振り回されるのではなく、キャリアを自分の手で切り拓く。
その主体性こそ、優秀な人が辞める最大の理由です。
公務員を続ける人が優秀な理由5選


優秀な人ほど公務員を辞めるイメージがありますが、公務員を続ける人にも、また違った優秀さがあると言えます。
1.逆境で踏ん張る粘り強さ
異動や制約に振り回されても、腐らずに成果を出し続けるのは並大抵のことではありません。
「どんな環境でも与えられた仕事をやりきる」という姿勢は、長期的に組織を支える大切な優秀さです。
2.長期的な視点で成果を育てる力
政策や制度は、結果が出るまでに数年〜数十年かかることも珍しくありません。
短期で評価されにくいなかでも粘り強く取り組める人は、社会にとって大きな価値を生み出しています。
3.調整力と人間関係構築力
住民、議会、上司、同僚…利害の違う人をつなぎ、合意をつくる力は公務員の現場でこそ磨かれるスキルです。
これはどんな職場に行っても通用する、隠れた“優秀さ”だといえます。
4.公共性を軸にぶれない価値観
「誰かの利益より、社会全体の利益を優先する」姿勢を持ち続けられるのは簡単なことではありません。
公共性を守る価値観は、長く公務員を続けてきた人だからこそ体現できる優秀さです。
5.制度・仕組みを熟知して活用できる力
行政の制度や法律を知り尽くし、それを正しく使えるのは続けてきた人の大きな強みです。
困っている住民に「この制度が活用できる」と即座に答えられるのは、継続して積み上げてきた証です。
公務員を辞めるか迷っているあなたへ


もし今、あなた自身が辞めるかどうか迷っているなら、一度立ち止まってみてください。
大切なのは「自分の”なりたい”優秀さはどっちか?」を考えることです。
挑戦する優秀さを発揮したいのか、支え続ける優秀さを発揮したいのか。
第一歩として、自分の価値観を整理することから始めるのがおすすめ。
実際に「自分の価値観マップ」を作ると、やりたいことや大事にしたいものが見えてきます。
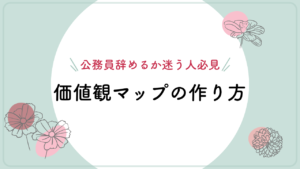
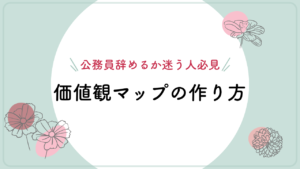



焦って答えを出す必要はないけれど、「選ばないままズルズル続ける」のが一番もったいないことです。
まとめ:公務員を辞める優秀さと続ける優秀さは異なる


「公務員を辞める人の優秀さと、公務員を続ける人の優秀さは違う」ということを紹介しました。
優秀な人が公務員を辞めるのは、決して逃げではありません。
専門性を活かしたい、組織の矛盾に耐えられない、自分の人生を自分で選びたい。
そうした強い思いが行動につながっているのです。
一方で、公務員を続けている人もまた優秀です。
長期的な視点で成果を積み上げ、公共性を守り、住民の生活を支える。
その継続力と価値観は、社会にとって欠かせないものです。
「公務員を辞めて外の世界へ」「公務員として根を張って住民の生活を支える」どちらも正解。
大事なのは、あなた自身がどんな想いで、どんな価値観で選択するかです。
この記事を読んだ今、少し立ち止まって考えてみましょう。



あなたはどちらの優秀さがお好みですか?





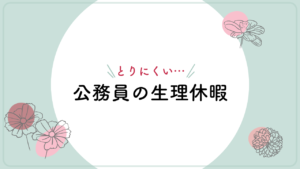

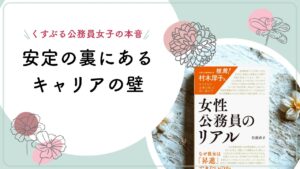
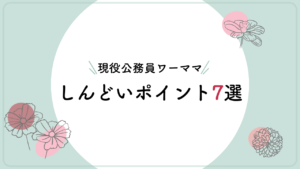
コメント